2025年6月13日(金)、当事務所は、ハートピア京都3階大ホールにて、田野大輔先生をお呼びして、「第21回憲法を活かす講演の集い」を開催しました。
講演では、まず「悪の相対化」というキーワードがあげられました。「悪の相対化」とは、例えば、“ヒトラーがユダヤ人を祖父に持つ少女をかわいがった話“を切り取り、「ナチス=絶対悪」という評価を相対化しようとすることです。「悪の相対化」は、「100%の悪など存在しない」「悪であっても何かいいところがある」という大衆が信じたいイメージに寄り添うプロパガンダの手法であり、ナチスやヒトラーを相対的に評価し、正当化してしまう危険性を述べられました。これは、現代にも通じるところがあり、人々は「教科書に書いていない真実」や「一般的な評価と異なる見方」といった「逆張り的な態度」に傾倒してしまうところがみられるとのことでした。
次に、田野先生が挙げられたキーワードは「悪の凡庸さ」でした。「悪の凡庸さ」はハンナ・アーレントがナチス戦犯アドルフ・アイヒマンの裁判を傍聴した際に用いた「自分自身も悪に加担し得るという自戒の概念」のことです。しかし、今日の日本において、「悪の凡庸さ」とは、「上の命令に従っただけで自分は悪くない」という責任回避の論理として利用されているとのことでした。私は、このことが、SNS特有の「誰かが言ったことを繰り返しただけ」という責任回避に通じるものがあると感じられました。
そして、講演の中では、田野先生が執筆された共同著書『検証 ナチスはよいこともしたのか』の内容についてもご紹介いただきました。同書はSNS上で蔓延するナチスに関する俗説(アウトバーン、少子化対策、禁煙政策など)を検証・反証するために執筆したとのことです。SNS上では、断片的な事実を繋ぎ合わせて「善の物語」が作られ、ナチス擁護論や誤った歴史認識が蔓延しており、これらに対しナチスの具体的な政策について検証しながら反論をすることが必要であると感じられたとのことでした。ナチスの「良い政策」と言われるその裏にある差別や暴力的支配、排除の構造について触れられていたのが印象的でした。
田野先生は、日本の政治においても「悪の相対化」が見られると指摘されました。例えば、兵庫県知事選では、感情的な共感やメディア不信が政治判断に影響を与えてしまったことを指摘されました。「一見、良い人そうに見えるから」という表面的な印象で政治家を判断してしまう傾向、また、「常識的な価値観に反発すること=真実への接近」と考える風潮について、危惧されていました。
現代社会は、SNSの普及により、誰もが発信者となることができ、断片的な情報をつなぎ合わせて都合のよい物語を構築してしまう「陰謀論的思考」も広まっているとのことです。但し、現代の「陰謀論的思考」については、意図的にデマや陰謀論を展開するのではなく、自分で調べた断片的情報をつなぎ合わせる「謎解き」や「物語」を構築する心理構造こそに問題があるとの指摘がされました。私は、情報の真偽を確認する努力を怠ることの危険性を改めて認識しました。
最後に、田野先生はこのような誤情報や歴史修正主義に対して、専門家が積極的に関わり、一つ一つ丁寧に反論を積み重ねていくことの重要性を説かれました。「間違った情報を信じてしまう人よりも、それを見聞きした周囲の人が誤解しないように働きかけることが大切」というお言葉が非常に印象に残っています。
私は、講演全体を通じて、歴史を正確に理解し、現在の政治や社会の問題を見つめ直すことの大切さを痛感いたしました。事実に基づいた冷静な議論を行い、感情や印象ではなく、根拠ある知識をもとに思考する姿勢を持ち続けたいと思います。



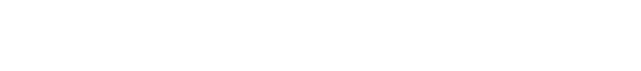
 弁護士
弁護士