民事・刑事での判断の違い -けんかによる死亡の因果関係―
事件の概要
Hさん(当時64才)は、平成10年10月1日、京都市内を走行中交通上のトラブルから、後に刑事被告人となるY氏に2キロほど車で追われたうえ、停止後、暴行を振るわれ、頭部を殴られ気を失って、救急車で運ばれた病院で意識不明のまま2週間後に死亡しました。
刑事裁判は傷害罪のみ
事件を捜査した検察庁は、なんとY氏を2週間の傷害罪で、つまり暴行から死亡までの間の期間の傷害罪でのみ起訴していたのです。死亡までの責任は問わなかったのです。そして、被告人Y氏は、刑事事件としては2週間の傷害罪で罰金刑で終了していました。実は、この当時は、被害者に対し検察庁から裁判の日程などを知らせる制度がまだなかったので、遺族は被告人が2週間の傷害罪のみで起訴されていること、判決が既におりていることなどなどまったく知らされていなかったのです。
民事裁判の提起まで
刑事事件が終了した後に、Hさんの内縁の妻KさんとKさんの子Nさんが、相談に来られ、暴行による死亡の損害賠償を求める民事裁判を提起することになり、検察庁に刑事裁判の確定記録を取り寄せました。そうしたところ、はじめて、傷害致死ではなくて、たった2週間の傷害罪で起訴・判決がなされていたことを知ったのです。
どうしてそのような結果になっているのか、記録を読んでみました。刑事確定記録の中に、Hさんの死体の解剖がなされた「鑑定記録」がありました。その中で、Hさんは過去に脳梗塞を発症したことが記録されており、鑑定の結論としては暴行と脳血管破裂の因果関係は認められるとしていたものの、脳の一部に死亡直前の暴行によるものではない脳細胞の壊死している病巣があったこと、また、被告人の頭部暴行の部位と脳出血の場所(出血場所は脳の表面ではなく中心に近いところであった)が離れているとされていました。鑑定人の意見としては、通常は起こりえない箇所での出血であるから相当強い外力が作用しなければいけないとしていました。その一方、Hさんは脳梗塞を発症したことがあるように血管が非常にもろくなっており、一定程度の外力が加われば脳の内部であっても出血する可能性はあると結論づけていました。
検察官は、慎重に起訴をするという姿勢を常にもっています。また検察官には、起訴裁量権限があるので、どのような起訴をするかは検察官にまかされています。脳表面に加わった外力と出血場所の懸隔(あいだ)の因果関係に自信がなかったのでしょう、そこで、間違いなく裁判所が認めるであろう傷害罪のみに絞って起訴していたのでした。
しかし、これでは遺族は納得できません。そこで、2001年9月、民事裁判を、傷害致死まで含めて提起することにしました。
民事裁判の中で
民事裁判を起こしましたが、残念だったのは内縁の妻であったKさんが、病気で裁判の結果を知る前に死亡してしまったことです。内縁の妻としての慰謝料はN さんが相続しました。
裁判の過程で、鑑定をした当時の大学の法医学教授だった鑑定人に鑑定時の様子を詳しく聞きました。鑑定人は、法医学の独自の立場から、暴行部位と出血場所の関係について様々な推論をしていることがわかりました。3回ほど聞き取りを重ね、暴行と死亡との因果関係について明確に存在するという確信を持ち、裁判に出席してもらうことにしました。そして、裁判所で、暴行と死亡の因果関係について解剖所見からみてどのような見解を持っているか詳しく証言してもらいました。証言では、Hさんは過去に脳梗塞となり、その原因としてそもそも脳血管が非常にもろくなっており、少しの振動でも破裂する危険があったことから、H さんの死亡が直接の暴行による出血かどうかは微妙な点が確かにあり、例えば2キロほど追いかけられている間の緊張から出血した可能性も否定できないが、暴行が無関係ではないとのことでした。
裁判所は、出血の原因がHさんが持っていた血管の異常等によるものではないかとの被告の主張に対しては、暴行前は脳の一部に壊死があるなど過去の脳梗塞の影響が残存していたとはいえ、まったく普通の生活をしていたのであり、本件出血は暴行によるものだと認定しました。ただし、持病の疾患についての相殺をし、請求から4割の減額がなされ、判決は確定しました。
刑事民事の違い
刑事事件は2週間の傷害のみというのは、遺族にとっては信じられない起訴でしたが、民事裁判で、ようやく暴行と死亡の因果関係が認められ、亡くなられたH さんの悔しい思いが晴れたという事件でした。
この当時は、被害者救済制度ができる直前であり、どのような刑事裁判がなされているかなど、被害者はまったく知らされない状態でした。今なら通知制度がありますので、不当な起訴と思えば検察庁に申し入れることも不可能ではありません。また、起訴そのものがなされていないのであれば、検察審査会に不起訴不当もしくは起訴相当を求めて、申し立てができます。諸外国では、民事事件と刑事事件が同時に進行するのでこのような分裂は起きないのです。さらに司法改革が必要な場面と思います。


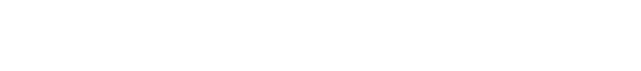
 弁護士
弁護士