第18回 憲法を活かす講演のつどいを開催しました
1 憲法を活かす講演のつどいを開催しました
2022年5月27日、名古屋大学大学院・教育社会学教授の内田良先生をお迎えして、「学校をカエル!校則改革・働き方改革からの展望」と題し、講演会を開催しました。
2 内田先生の講演
⑴ リスクに盲目的な学校現場
「大人の制度設計のミスで、傷つくのは子ども。そんな状況を変えたい。」内田先生のお話の根底には、この一貫した想いがありました。
内田先生が、「スポーツにケガはつきものだから」で済まされてきた部活中の事故を分析し、たとえば「過去31年間に発生した118件の柔道死亡事故には、中学1年生か高校1年生が、5月~8月にかけて、大外刈りで投げられて死んでいるものが多い」ということを公表すると、大きな反響を呼びました。柔道を始めたばかりの初心者に上級生の相手をさせないようにすること、大外刈りに注意することが、リスク回避のために必要な対策です。
組体操における事故も同様です。1段、2段と積みあがっていく人間ピラミッドは、見る者を感動させます。しかし、一番下の生徒にかかる負担が非常に大きいことは、物理的な計算で数値として分かることです。にもかかわらず大人は、リスクが高ければ高いほど、それを乗り越えたときの感動は大きいからと、生徒らに「頑張れ」と言って、1段、また1段と高いピラミッドを要求します。生徒にかかる負荷を計算しようとせず、ピラミッドが崩れて大怪我をした子がいるという事実すら見ようとしないのです。何かを犠牲にした上での感動は要らないと、内田先生は訴えます。
⑵ 過労死ラインを超える教員の働き方
そして、そのことは教員にも同じことが言えます。
教員の労働時間は、国の調査によれば、5~6割が過労死ラインを超えています。その理由は2つあります。1つは、教員の給料の仕組みです。給特法によって、基本給に4%の給料を上乗せして超過勤務手当とし、いくら働かせても、そこにコストが発生しない仕組みを作り上げています。まさに「定額働かせ放題」です。いくら働かせても給料には関係ないのですから、タイムカードによって時間管理をする必要もありません。多くの学校では、出勤簿に印鑑を押して、「今日も生きています」と申告するだけで良かったのです。
もう1つは、教員の意識です。2016年、現役教員がTwitterで「部活しんどい」と呟くと、瞬く間に賛同の声が広がりました。職員室では、時間もお金も関係なく、生徒たちのために働くことが教育者の美徳とされており、もし同じことを職員室で呟けば、「あなた何のために教員になったの?」と言われるような雰囲気です。だからみな、匿名のSNSで呟くほかないのです。
長時間労働の結果、心身に不調をきたす等して、1人また1人と職員室を去ってゆきます。しかし、教員が自分自身の生活や心身の健康を犠牲にしなければ「教育」は実現できないのでしょうか。
⑶ 「ブラック校則」に繋がる「学校依存社会」
そもそも、なぜ教員が、時間もお金も関係なく働かなければならないような状態に置かれるのか。その理由の一つに、学校が家庭や地域社会からの「要請」を無限定に引き受けさせられていることが挙げられます。これを、内田先生は「学校依存社会」と表現します。
教育は、学校だけで行うものではありません。家庭や地域において、親や周囲の大人と関わる中で、一般常識や社会性を身に着け、自ら考え行動できる自立した人間に育ってゆくこともまた教育です。しかし、家庭や地域社会は、子どもが「至らない」ことを学校の責任にしてはいないでしょうか。
そのことは、「午後4時まで(自宅から)外出禁止」という校則にも表れています。つまり、生徒が制服を着たまま午後の早い時間帯にフードコートで集まっていると、それを見た地域の人達が学校に「どういう教育をしているのか」と苦情の電話を入れるのだといいます。そのため、学校は生徒が学校の門を出ても管理する校則を作るのです。そして、それが、ヘアカラーやパーマの禁止、丸刈りの強制、白い靴下の強制等、過度に学生の自由を奪う「ブラック校則」に繋がっていきます。
⑷ 学校を批判する前に
とはいえ、「学校のやっていることは人権侵害だ」というところからスタートしても、学校は変わりません。忘れてはいけないのが、学校はこれが望ましい対応だ、生徒を守るための対応だと思ってやっていることだと、内田先生は強調します。
例えば、ツーブロックが禁止なのは、街でトラブルに巻き込まれるかもしれないと心配してのことです。生まれながらに茶髪やパーマである子に地毛証明書を求めるのは、教員が誤った指導をしないようにするためです。そういう面を無視して批判しても、何も知らない第三者の批判だ、と捉えられてしまいます。
学校が何故そのような指導をするのか、何を目的とした校則なのかということからスタートして、本当に必要な規則なのか、根拠としている事実があるのか等を、一緒に考えていかなければなりません。
⑸ 校則を変えるのは生徒か、教員か
奇しくもコロナ禍で、校則改革の動きが加速しました。ウィルスを除去するためには洗濯しやすい方が良いということで、制服を標準服化し、私服での登校が可能になった例もあります。生徒が声をあげてブラック校則が変わったとき、ニュースで大々的に報道されます。
しかし、生徒が声をあげても校則が変えられなかった事例はたくさんあります。「腕まくり」を認めてもらうのに1年かかった。ベージュに加えて黒のタイツを認めてもらうのに8か月かかった。それで良いのでしょうか。
校則はないけれど、他者に対する加害行為をした場合、警察に通報して対応してもらうという学校もあります。一見、厳しいように感じますが、一般の社会で他人に暴行を加えたり人格を否定したりすれば、「いじめ」ではなく「暴行罪」ないし「侮辱罪」です。他人の物を壊せば「器物損壊罪」であって弁償しなければなりません。それが「学校」という場で起こったからといって、学校内で解決すること、すなわち教員に警察や裁判所の役割を担わせることに合理性があるのか疑問です。
学校が生徒を否定し続けるのか、肯定するのかが問われています。今は、個性や多様性を尊重しようという社会です。内田先生は、学校(教員)がもっと子供を信じ、憲法の理念に則って、自由を最重要項目にして接しても良いのではないかと訴えます。
⑹ 治外法権化する「学校」という場
他方、「学校」という場で起こると不問に付されることが、他にもあります。それは、指導と称して行われる体罰や、スキンシップと称して行われるわいせつ行為です。わいせつ行為については、過去には免職にならなかったものが、近年は2件に1件が免職となっていますが、体罰で免職になった例は今も昔もほとんどありません。「教育」「指導」が行き過ぎたものとして済まされてしまうのです。
⑺ 「部活動」を見つめなおす
また、15時30分を境に、それまで禁止とされていたことが、「部活動」ということで解禁されることもあります。たとえば、学校生活では「廊下を走るな」と指導されていますが、15時30分から運動部の活動が始まると、体力作りやウォーミングアップと称して生徒たちが階段を駆け上がります。それを誰も咎めません。当然、歩行者とぶつかって怪我をするケースが出てきます。
また、水泳の授業では飛び込み禁止と指導されています。学校のプールは溺れないよう浅くなっており、危険だからです。しかし、15時30分から水泳部の活動が始まると、生徒たちは次々と飛び込みます。実に半数の生徒が、飛び込みで頭をぶつけたことがあると回答しています。
その他にも、授業用の狭いグラウンドに、様々な部活動の練習を同時に押し込めた結果、陸上部員の投げたハンマーがサッカー部の部員を殺したこともありました。明らかに大人の制度設計のミスで生徒が傷ついているのに、そこでは怪我をさせた生徒、怪我をした生徒が、「どこを見ていたのだ」と責められます。
運動部の顧問の半数は、競技経験がないといわれています。2017年に、登山部の高校生7人が雪崩に巻き込まれて死亡した事故でも、引率教員は競技経験がなく、剣道部と顧問を掛け持ちしていた入職1年目の教員でした。その教員自身も同事故で亡くなっています。
国語や数学といった教科の授業は、学校における教育課程内にある活動で、その目的に沿って、学習指導要領で内容がかっちりと制度設計されています。しかし部活動は、教育課程外の活動で、やってもやらなくても良い自主的なものです。したがって、生徒たちの安全に配慮した制度設計がなされておらず、上記のような事故をしばしば起こします。しかし、学校は数を競うように屋上から、「全国大会出場」「インターハイ準優勝」といった垂れ幕をおろします。自主的な領域は時として過熱し、暴走すると内田先生は指摘します。
そもそも、部活動は何のためにやっているのでしょうか。とある高校は、週に3日しか練習しないのに、ラグビーの全国大会に出場しました。試合中、教員は口を出しません。勝つための作戦を生徒たち自身に考えさせます。負ければ、何が足りなかったのか、それを考えるのも生徒たちです。勝ち負けではなく、考える力を育む。それで部活動の目的は達せられるのではないでしょうか。
⑻ みんな本当は「しんどい」と思っている
いじめの調査研究によれば、いじめ加害による出席停止は年間1件であるのに対し、いじめ被害による不登校は年間483件にのぼります。なぜ被害者が普通の生活を送ることができなくなるのか、教員に匿名のアンケートをとると、加害者を出席停止にすべきだという回答が圧倒的多数を占めます。部活動はこの20年~30年でどんどん加熱してきました。その顧問をやりたいかと教員に匿名のアンケートをとると、半数は「やりたくない」と回答します。
教員個々人は、学校(教員)で何もかも抱えることに限界を感じています。しかし、組織は「生徒のためにやらなければならない」という答えしかない。そこに問題があります。 みんな「学校を変えたい」と思っています。だから教員の皆さん、動き出しませんか。内田先生は優しい眼差しで訴えかけ、講演を終えました。
3 パネルディスカッション
後半は、内田先生と、現役教員であり京都教職員組合の星琢磨先生、当事務所の渡辺弁護士のパネルディスカッションを行いました。
星先生は教員15年目。入職した年は、初任者研修に加え、担任業務と16学級の授業、部活動を受け持ち、教育実習生のお世話も重なっていたといいます。「生徒たちのために、中途半端な授業はできない。授業研究をしっかりやらないと。」と、その年の6月には超過勤務が60時間以上にのぼっていました。
京都府の令和2年度の平均残業時間は月76時間で、過労死ラインぎりぎりです。しかし、ここには持ち帰り残業が含まれていません。そのことを理解していながら、教育委員会は、「前年より少し減って良かった」という呑気な受け止めです。もともと学校現場に余剰人員はなく、休職者が出ると代替要員は来ず、助け合う余裕がない。その結果、同僚のしんどさに気付けず、また新たな求職者を生み、負のスパイラルなのだといいます。そのような過酷な労働実態が、深刻な教員不足に繋がっています。2022年3月末退職者は204名で、うち定年前は93名(45.6%)、30代~40代の離職者も多い状況です。
今、内田先生も関与して、部活動の地域移行に関する議論が動き出しつつあります。我々地域社会、保護者の側も、教育の全てを学校に依存するのではなく、学校とともに教育に関与していくことが大切です。


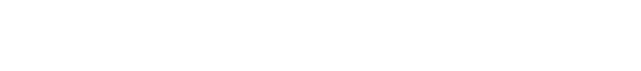
 弁護士
弁護士