1 30年前の団交闘争
京都市は、学童保育を委託や指定管理で運営していますが、委託先、指定管理先で働く職員の賃金や労働条件については、京都市が自ら定める要綱で規定し、その費用も負担することで、労働者の労働条件を守ってきました。
1989年、職員の労働条件の改善のためには、要綱を定める京都市と直接交渉する必要があり、福保労は京都市に団体交渉を申し入れました。これに対して京都市が、直接の雇用関係にないと言って拒否したことから、福保労は、京都地方労働委員会に不当労働行為の救済申立てを行いました。地労委の手続が進む中で、京都市は自ら団体交渉に応じることを認め、京都市と福保労との団体交渉が始まりました。その後30年間、京都市と福保労との団体交渉が続けられてきました。
2 再度の団交拒否と府労委の一部救済命令
2020年4月、京都市は、福保労との交渉も経ずに、職員の労働条件に関わる要綱の改悪を行いました。福保労が抗議し、団体交渉を申し入れたところ、京都市は、直接の雇用関係にないと、30年前に遡ったような回答で団体交渉を拒否してきました。
福保労は、京都府労働委員会に対して、再び不当労働行為の救済申立てを行いました。審理の結果、2022年6月1日、府労委は、一部の労働者について、京都市に対し、団体交渉に応じるよう命ずる一部救済命令を出しました。形式的には、京都市と各組合員との間に雇用契約はありませんが、一部の労働者については、1989年に京都市が自ら団体交渉に応じ、労使関係にあることを認めたこと、その後30年にわたって団体交渉が行われてきたこと、一部労働者については要綱によって自動的に労働条件が定まる構造にあったことなどを認め、京都市に労組法上の使用者性を認めた画期的な命令が下されました。
3 府労委命令に応じない京都市と損害賠償請求訴訟
福保労は、京都府労委の命令を受けて、ただちに京都市に対して団体交渉を申入れました。しかしながら京都市は命令に従わず、団体交渉拒否を続けました。福保労は、京都市が命令後も団体交渉拒否を続けていることが不法行為にあたるとして、京都地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。
2023年12月8日、京都地裁は、福保労が京都市との団体交渉について強い期待を有しており、その期待を侵害したことは国賠法上違法であるとして、京都市に対し30万円の賠償を命じました。府労委の命令が確定する前の段階での団体交渉拒否について国賠法上の違法性を認めた画期的な判断でした。
この判決に対して京都市が大阪高裁に控訴したところ、大阪高裁は、一部の争点について審理が不十分であるとして、京都地裁に差し戻すとの判決を行い、現在、京都地裁での審理が続いています。
4 府労委命令を維持した京都地裁判決
他方で、府労委命令に対しては、京都市と福保労の双方が、京都地裁に取消訴訟を提起しました。福保労としては、一部の労働者だけではなく、京都市内のすべての学童保育所・児童館職員との関係で、京都市が労組法上の使用者と認められるべきであると主張して訴えを提起しました。
2025年6月24日、京都地裁は、京都市と福保労の双方の訴えを退け、府労委命令を維持する判決を下しました。一部の労働者が雇用される運営団体(京都市学童保育所管理委員会)の性格や、1989年当時、京都市が自ら団体交渉に応じ、以後、京都市が使用者として30年にわたって団体交渉を行ってきたこと、労働者の賃金が京都市の算定通りに支払われていることなどを捉えて、京都市が、当該運営団体の職員の賃金について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にあったと認定したのです。
一部の労働者に限られるとはいえ、直接の雇用関係にない労働者について労組法上の使用者性を認める画期的な判断が、府労委に引き続き、京都地裁でもなされました。闘いは大阪高裁に移りますが、一日も早く京都市に団体交渉に応じさせ、学童保育所・児童館で働く職員の労働条件に責任を持たせるように力を尽くします。
(当事務所の担当弁護士:大河原、秋山、藤井、谷)

報告集会


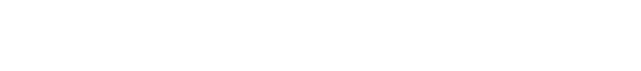
 弁護士
弁護士