1 公務中の転倒事故なのに、なぜか公務外
京都市職員のAさんは、外回りの勤務中、水道工事のため仮舗装となっていた道路で、舗装の継ぎ目でつまずき、顔面から転倒して、左顔面挫創、左膝・右拇指挫創の怪我を負いました。顔を7針も縫うほどの怪我でした。公務中に起こった事故なので、当然、公務災害に認定されるだろうと思い、公務災害申請を行いました。ところが、地方公務員災害補償基金京都市支部(基金支部)は、「災害発生時の動作は日常動作の範囲内であり、災害性が認められない」として公務起因性を否定し、公務外と認定したのです。
Aさんは、基金支部の公務外認定を不服として、支部審査会へ審査請求を行いました。ところが、支部審査会でも「転倒の原因となるような特異又は突発的な動作がなく、舗装中の道路であったことを考慮しても、公務が他の原因に比較して相対的に有力な原因であると認められない」として、やはり公務起因性を否定し、Aさんの審査請求を棄却しました。
しかしながら、今回の転倒事故は、Aさんがわざと転んだものでもなければ、Aさんに何らかの素因があったわけでもありません。当然に公務起因性が認められなければならないはずです。Aさん自身も、なぜこれが公務災害として認められないのか、との素朴な疑問から再審査請求を行いました。
2 労災と公務災害では認定基準が違うのか?
本件では、Aさんが加入する京都市職労のほか、京都自治労連や京都職対連が支援を行っていました。京都職対連は、公務災害だけではなく民間の労災の支援も行っています。労災であれば、業務中の転倒事故について労災認定が受けられないなどということは考えられない、というのが支援の現場の実感でした。
そこで、労災を管轄する厚労省と、公務災害を管轄する総務省の双方からヒアリングを行うこととなりました。倉林明子参議院議員(当時)を通じて、厚労省と総務省の双方をオンラインでつなぎ、労災と公務災害の認定の実態についてヒアリングを行いました。
まず、労災と公務災害について、その制度趣旨が同じであることを双方から確認しました。その上で、同じ状況で起きた災害について、労災と公務災害で認定に差が出るのかと尋ねると、総務省は「同様の考え方に基づいて認定を行っているため、差が生じるということは基本的にないと考えている」と答えたのです。
それを踏まえて、本件のような「何もないところでつまずいて転倒した事例」について厚労省に尋ねたところ、「業務に就いていることに伴う危険が現実化したもの」として業務起因性が認められると答えます。これに対して総務省は「何もないところでつまずいて転倒するのは、一般的には、経験則上、危険が現実化したものとは考えられにくいところと考えている」と述べ、実際の認定の場面では異なる実態となっていることが明らかとなりました。
3 再審査請求での逆転勝利裁決
再審査請求では、厚労省・総務省ヒアリングで明らかになった、労災と公務災害との認定の実態の違いも示して、本件で公務起因性を否定した原処分や支部審査会裁決を批判しました。
再審査請求に対して基金本部は、「本件のように、舗装工事中の道路を歩行中に道路の凹凸や段差に躓いて転倒することは、段差の程度等にかかわらず、一般的に起こりうることであり、本件災害において、請求人が明らかに公務と関係のない恣意的行為を行っていた又は請求人に転倒の原因となるような素因があった等の事情も認められない。したがって、本件災害は公務に内在する危険が現実化したものと認められる」として、基金支部や支部審査会での公務外の判断を覆して、公務上の災害と認定したのです。
労災での認定の実態や、公務起因性についての本来の判断基準からすれば当然の判断ではありますが、基金支部や支部審査会での判断を逆転して、公務上の災害と認定されたことは大変意義のあるものです。同じような転倒事故で、「日常動作の範囲内」だと言われて、公務外とされたり、または、公務災害申請自体を諦めさせられるようなことのないよう、引き続き取り組んでいきたいと思います。



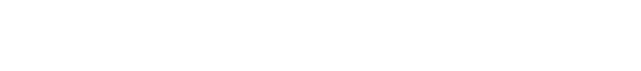
 弁護士
弁護士