1 事案の概要
Aさんは長年うつ病の治療を受けており、一時は障害者手帳2級を取得していましたが、症状が回復したため、障害者雇用枠で就業を再開していました。さらに症状が回復し、障害者手帳も3級に変更できたため、一般就労の雇用先を探していました。そうしたところ、ハローワークを通じてB社の運送ドライバーの仕事を紹介され、採用面接などを経てB社と労働契約に至りました。面接の際にはうつ病であることも伝えていました。
ところが、就労開始直後に、障害者手帳の所持を理由にB社から解雇通知を受けたというものです。ただ解雇通知を受けた際に、Aさんは退職に必要な書類だと説明を受けて、退職届を作成させられてしまいました。そのため、B社は解雇の事実を争い、Aさんが退職届を書いているとおり、合意に基づく退職だと主張していました。そこで、Aさんが当事務所に相談に来られ、当職が担当しました。
2 争点
訴訟では、主位的には解雇無効を争いつつ、予備的にB社の退職勧奨が障害者雇用促進法に違反するとして退職無効を主張し、また障害者差別に当たるとして慰謝料の請求をしました。
障害者雇用促進法は、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならないと定めており(同法35条)、厚生労働大臣は、障害者差別禁止指針を定めています(同36条1項)。同指針では、募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新と多岐に亘り、障害者差別を禁止しています。ただ、これに違反した場合にも罰則はなく、行政からの助言や指導、勧告にとどまります。また不法行為の成否など民事上の違法性については明らかではありませんでした。
3 判決
京都地裁では、解雇の事実は証拠上認められないとし、退職無効についてもAさんの主張を退けました。一方、Aさんが「精神障害等級3級との認定を受け、通院して服薬治療を受けていることのみをもって、その病状の具体的内容、程度は勿論、主治医や産業医等専門家の知見を得るなどして医学的見地からの業務遂行に与える影響の検討を何ら加えることなく、退職勧奨に及んだ」ことについて、「障害者である原告に対して適切な配慮を欠き、原告の人格的利益を損なうもの」であるとして、不法行為の成立を認め、慰謝料として80万円の支払を命じました。大阪高裁も地裁の判断を支持し、最高裁で判決が確定しました。
4 障害を理由とする退職勧奨に歯止めをかける判決の意義
残念ながらAさんの希望していた解雇や退職の無効は認められませんでした。
しかし、退職勧奨に基づく退職合意が有効とされた場合であっても、退職勧奨の手続に問題があれば違法性を問うことができ、不法行為に基づく慰謝料請求が認められる事例判決を得ることができました。この判決は労働事件を扱う主要な判例雑誌「労働判例(2025.5. 15.No1327.92頁)」にも掲載をされ、今後、差別的な退職勧奨に歯止めをかける社会的に意義のある判決となったと考えています。
最後に、本来であれば障害者雇用促進法に違反するものとして違法性が認められるべきところ、判決の中で同法への言及がなかったことは残念であり、この点も今後の課題として残った点となります。


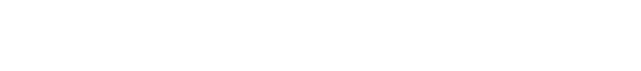
 弁護士
弁護士